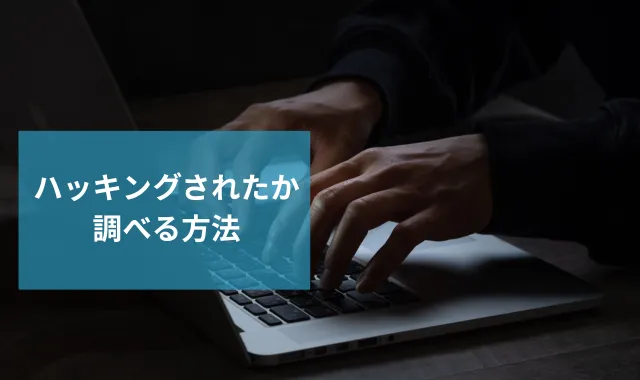
ハッキングされたか調べる方法8選!被害に遭った際の対処法も解説
ハッキング被害は、気づかないうちに個人情報や金銭が盗まれ、深刻なトラブルに発展する恐れがあります。
本記事では、自分の端末がハッキングされたか調べる方法や、被害時の具体的な対処法、今後の予防策までをわかりやすく解説します。
読み終える頃には、「何をすべきか」が明確になり、不安を安心へと変えるための知識が身につきます。
ハッキングされたか調べる方法

ここでは、ハッキングされたか調べる方法を8つ紹介します。
スマホ・パソコン本体に異常がないか
まず確認すべきは、使用しているスマホやパソコン自体に不自然な挙動がないかです。
例えば、以下の症状が見られる場合は注意が必要です。
- 端末が異常に熱を持っている
- 動作が重くなった
- バッテリーの減りが異常に早い
上記のような現象は、バックグラウンドで不正なプログラムが動作することで発生している可能性があります。
とくにマルウェアに感染している場合、ユーザーが気づかないうちに端末内でデータの送受信や、遠隔操作が行われることがあります。
これによりスマホやパソコン本体の負荷が上がり、端末が熱を帯びたり、バッテリーの消耗が早まったりすることが多いです。
勝手にメッセージを送っている
自分が送った覚えのないメッセージが、SNSやメール、チャットアプリで知人に送られている場合は、端末やアカウントが不正に利用されている可能性があります。
とくに「こちらのURLを確認してください」などとリンクが記載されたメッセージが送られている場合、そのリンク先がフィッシングサイトであることも少なくありません。
このようなケースでは、被害が自分だけに留まらず、メッセージを受け取った相手が詐欺サイトへ誘導されたり、ウイルスに感染したりなどの二次被害が発生するおそれがあります。
データ通信量や電話料金が増えている
普段と比べてデータ通信量が急増していたり、身に覚えのない通話料が発生していたりする場合も、ハッキングされている可能性があります。
通信量や通話料の増加から、端末がマルウェアに感染してユーザーの知らない間に通信や通話を行っているケースが考えられるためです。
また、悪質な手口の中には、ユーザーに気づかれないよう自動的に国際電話を発信させるものもあります。
これにより高額な料金が発生するだけでなく、通話を通じて端末の位置情報を取得される恐れもあるのです。
知らないアプリが入っている
インストールした覚えのないアプリが端末内に見つかった場合は、ハッキング被害に遭っている可能性が高いです。
ゲームや便利ツールを装ったアプリの中には、実際には個人情報を収集するためのマルウェアが潜んでいるケースもあるので注意が必要です。
不正アプリはスマホ内の連絡先や写真、位置情報などと勝手に連携し、クレジットカード情報やオンラインバンキングの認証情報を盗み取ることもあります。
なかには、端末のセキュリティを弱めるために、インストール済みのウイルス対策ソフトを無効化またはアンインストールする悪質なものも存在します。
クレジットで勝手に購入されている
クレジットカードの利用明細に、身に覚えのない購入履歴がある場合は、すでに不正利用の被害が発生している可能性があります。
最近では、アプリやオンラインショップにカード情報を登録しているケースが多く、そこから情報を抜き取られ、悪用される事例が増加しています。
クレジットカードの利用明細はこまめにチェックし、不審な購入履歴を見つけた際は、カード会社にすぐ連絡することが必要です。
また、アプリやオンラインサービスを活用してリアルタイムで確認する習慣をつけておくと、不正利用にすぐに気がつくため安心です。
2FAコードが表示される
2FAコードが表示される際も、ハッキングされている危険性があるので注意が必要です。
2FAコードとは、パスワードに加えてSMSや認証アプリで送信されるコードを入力することで、アカウントを保護する仕組みです。
この2FAコードが、ログイン操作をしていないにもかかわらず届いた場合は、第三者があなたのアカウントに不正ログインを試みている可能性があります。
とくにGoogleアカウントやLINEなど、日常的に使用するサービスから認証コードが届く場合は要注意です。
パスワードが漏えいし、実際にログインされかけている状況であることが多く、放置すると乗っ取り被害に発展しかねません。
カメラやマイクが勝手にオンになる
操作していないのにスマホやパソコンのカメラ、マイクが勝手に起動する場合は、外部からの不正アクセスを受けている可能性があります。
遠隔操作型のマルウェアに感染すると、利用者の許可なく映像や音声を取得され、プライバシーの侵害や情報漏えいにつながる危険があります。
例えば、カメラ付近のランプが点灯している、通話アプリを開いていないのにマイクが使用中になっているといった状況は要注意です。
不正アプリのなかには、機能には関係ないにも関わらず、マイクやカメラにアクセスして相手の個人情報を盗むものもあります。
スマホを再起動するよう要求された
メッセージや通知で「スマホを再起動してください」と指示される場合は注意が必要です。
携帯キャリアを装ったSMS・メールでこのような要求が届く場合、SIMカードが乗っ取られている可能性があります。
突然、スマホの再起動が促される場合、第三者が不正にSIMの再発行を行い、あなたの電話番号を使って認証コードを受け取ろうとしている可能性が高いです。
万が一、再起動をしてしまうとスマホの情報が乗っ取られ、銀行口座や各種サービスのアカウントが盗まれてしまいます。
ハッキングされたか調べられるサイト2選
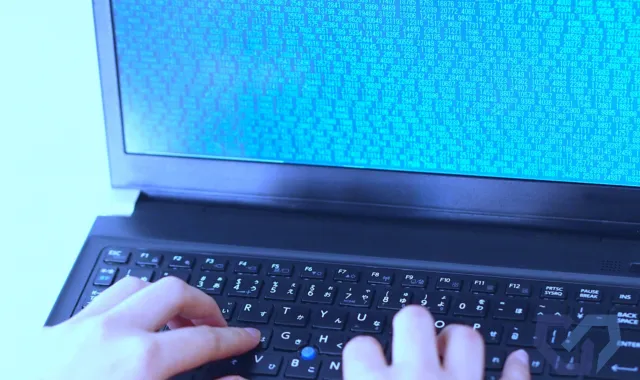
自分のアカウントが不正利用されていないかを確認する際は、以下2つのWebサイトの利用が便利です。
| サイト名 | 概要 |
| Have I Been Pwned | 登録したメールアドレスが過去の情報漏えいで流出していないか確認できる。メールアドレス入力だけで簡単に確認可能。 |
| Googleセキュリティ診断 | Googleアカウントのセキュリティ状態を診断できる。Googleブラウザをよく利用する人、カード情報を記録している人、Androidユーザーに特に有効。 |
ただし、これらのツールで確認できるのは、アカウントの不正利用の有無やアドレス情報が流出していないかに限られます。
スマホ本体やパソコン本体がハッキングされているかどうかまでは調べられません。
ハッキングのよくある手口

ハッキングの被害に遭わないためには、手口を理解しておくことが大切です。
ここでは、ハッキングのよくある手口を解説します。
フィッシング詐欺
フィッシング詐欺とは、実在するサービスや企業を装い、偽のWebサイトやメールを使って個人情報を盗み取る手口です。
代表的な例として、カード会社や金融機関を名乗り「不正利用の疑いがあるため、確認してください」といった内容のメールを送り、記載されたリンク先に誘導します。
リンク先は本物そっくりに作られた偽サイトで、利用者がログインIDやパスワード、カード番号を入力すると、その情報が攻撃者に渡ってしまいます。
フィッシング詐欺は、見慣れたロゴやデザインを使用し、利用者の警戒心を解きほぐすのが特徴です。
少しでも不審なメールやSMSを受け取った場合は、リンクを開かず、公式サイトやカード会社のサポートへ直接確認しましょう。
また、送信元アドレスやURLが正規のものであるか、常に確認する習慣を持つことが被害防止に有効です。
フリーWi-Fiからの侵入
カフェや駅、空港などで提供されるフリーWi-Fiは便利な反面、セキュリティが十分に確保されていないことが多いです。
実際、総務省が公表している「無線LAN(Wi-Fi)のセキュリティに関するガイドライン」でも、セキュリティ対策を行わないWi-Fiの利用に関して危険性が指摘されています。
例えば、公衆Wi-Fi接続時にSNSのログイン情報入力を求められ、入力した結果アカウントが乗っ取られるといった事例もあります。
フリーWi-Fiを利用した被害を防ぐには、暗号化されていないネットワークは利用しない、パスワード入力を求める通信は利用しないなどの対策が不可欠です。
SIMスワップ
SIMスワップとは、他人になりすまして携帯電話会社からSIMカードを不正に再発行し、スマホを乗っ取る手口です。
攻撃者は、偽造された身分証明書や個人情報を利用し、携帯会社に対して「SIMカードを紛失したので再発行したい」と依頼します。
携帯会社がこれを承認すると、攻撃者の手元に新たなSIMカードが届き、被害者の電話番号が乗っ取られる仕組みです。
具体的な手口は次のとおりです。
- 攻撃者がフィッシング詐欺や情報漏えいによって被害者の個人情報を入手
- 偽造身分証を用意し、携帯会社にSIM再発行を申請
- 攻撃者の手元に再発行されたSIMが届き、被害者のスマホが突然圏外になる
- 攻撃者がSMS認証コードを使い、金融口座やSNSを次々と乗っ取る
スマホが突然圏外になった場合は、すぐに携帯会社に連絡してSIMスワップの可能性を確認しましょう。
クロスサイトスクリプティング
クロスサイトスクリプティングとは、Webサイトの脆弱性を悪用し、ユーザーのブラウザ上で不正なスクリプトを実行させる攻撃手法です。
ECサイトや会員制サイトで多く見られ、ユーザーが気付かないうちに罠が仕掛けられるため、被害に遭いやすいという特徴があります。
例えば、攻撃者が商品レビュー欄や問い合わせフォームに、悪意あるコードを埋め込むことがあります。
コードが埋め込まれた画面をユーザーが表示すると、埋め込まれたスクリプトが自動で実行され、ログイン情報やクレジットカード情報が盗まれる仕組みです。
さらに、ユーザーが偽の支払いページへ誘導され、決済情報を入力させられるケースもあります。
こうした攻撃は利用者側では発見が困難なため、利用するWebサイトが信頼できる運営元かを確認し、ブラウザやセキュリティソフトを常に最新の状態に保つことが重要です。
ハッキングされた際の対処法

実際にハッキングの被害に遭った際は、早急に対処が必要です。
ここでは、ハッキングされた際の対処法を解説します。
セキュリティソフトを実行する
ハッキングの疑いがある場合、まず行うべきなのがセキュリティソフトの実行です。
セキュリティソフトを利用すれば、端末内で不正に動作しているマルウェアやスパイウェアを検出し、削除できます。
とくにバックグラウンドで情報を盗み取るタイプのマルウェアは目視では発見が難しいため、信頼性のあるソフトでのスキャンが不可欠です。
すでに感染が疑われる場合は、セキュリティソフトの駆除後に再起動し、再度スキャンを行うと、残存している不正ファイルを取り除ける可能性が高まります。
不正利用がある場合はカード会社に連絡する
クレジットカードやデビットカードの利用明細に覚えのない請求がある場合は、すぐにカード会社へ連絡してください。
迅速に利用停止の手続きを行えば、これ以上の被害拡大を防げます。
また、早期に報告することで、不正利用分の請求がキャンセルされる可能性もあります。
カード会社によっては不正利用補償制度があるため、詳細を確認しておくと安心です。
ただし、不正利用の補償は明細通知から60日以内など制限が設けられているので、早めの連絡が不可欠です。
パスワードを変更する
ハッキングの可能性があると感じたら、まずパスワードを即座に変更しましょう。
とくに同じパスワードを使い回している場合、1つのアカウント流出によって、クラウドストレージやオンラインバンキングなど、重要な個人情報にまで被害が及ぶ危険があります。
パスワードを変更する際は、推測されにくい複雑な文字列に設定してください。
具体的には、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた12文字以上を設定することが大切です。
また、2FAコードの設定も合わせて行うと安心です。
これにより、仮にパスワードが流出しても、スマホ端末から承認が必要になるため、不正ログインを防げる可能性が大幅に高まります。
システムの復元やOSのアップデートを行う
ハッキングの被害が疑われる場合、最終手段としてパソコンやスマホを工場出荷時の状態に戻すシステムの復元を行うのも有効です。
不要なアプリや不正プログラムを完全に削除できるため、内部に潜んだマルウェアを取り除ける可能性が高まります。
また、日常的な対策としてOSのアップデートも重要です。
古いバージョンのOSは、既知の脆弱性を突かれて攻撃される危険性が非常に高くなります。
最新のアップデートにはセキュリティを高めるプログラムが含まれているため、定期的な更新を怠らないことが大切です。
キャッシュやCookieを削除する
ハッキングの疑いがある場合は、キャッシュやCookieを削除しておくことも重要です。
キャッシュとは、Webページの表示を早くするために保存されるデータの一時ファイル、Cookieとは、Webサイトの設定情報やログイン状態を保持するための小さなデータです。
これらが端末内に残っていると、不正アクセスを受けている際に、保存されているCookieを悪用され、再び個人情報が抜き取られる危険があります。
不要なデータを定期的に消す習慣を持つことで、被害の再発防止にもつながります。
インターネットの接続を遮断する
ハッキングの被害が疑われる場合、まず行うべき応急処置のひとつがインターネット接続の遮断です。
Wi-Fiやモバイルデータ通信をオフにしたり、物理的にLANケーブルを抜いたりすることで、外部からの侵入や遠隔操作を防げます。
また、マルウェアが内部情報を送信している可能性がある際は、これ以上のデータ流出を食い止めるのに効果的です。
ただし、これはあくまで一時的な対策であり、根本的な解決にはなりません。
接続を遮断した後は、セキュリティソフトでのフルスキャン、パスワードの変更、OSやアプリのアップデート、専門業者への相談など、抜本的な対策を講じる必要があります。
デジタルフォレンジック調査を依頼する
ハッキングの痕跡を正確に把握したい場合、デジタルフォレンジック調査を検討しましょう。
デジタルフォレンジックとは、パソコンやスマホなどの端末を専門的に解析し、侵入方法や、持ち出されたデータを明らかにする調査手法です。
自力での確認では見落としがちな不正アクセスの痕跡や、削除されたデータの復元も可能で、被害状況の全容を把握するのに役立ちます。
被害が広範囲に及んでいる可能性がある場合や、重要なデータが扱われている端末では、早期に専門家へ相談することが被害拡大を防ぐうえでも重要です。
デジタルフォレンジック調査は探偵に依頼がおすすめ

デジタルフォレンジック調査を依頼する際は、探偵を利用するのがおすすめです。
探偵は専門的な知識をもとにハッキング被害の解決を最短で進め、加害者の特定や法的対応を見据えた証拠収集まで行えるためです。
具体的な探偵を利用するメリットを以下を参考にしてください。
- 加害者特定まで踏み込んで調査
- 裁判で証拠として利用できる報告書を作成
- 弁護士連携で法的措置へ橋渡しが可能
- 被害拡大を予防する専門的な措置を実施
- 再発防止策の提案
探偵は、端末解析の事実把握にとどまらず、加害者の特定し解決し、その先の法的アクションまで伴走できる点が大きなメリットです。
ハッキングを予防する方法

日常的な対策を徹底することで、ハッキングの多くは未然に防ぐことが可能です。
以下に主な予防策とポイントをまとめました。
| 対策 | 解説・ポイント |
| OSを常にアップデートしておく | アップデートには既知の脆弱性を塞ぐセキュリティ修正が含まれる。更新を怠ると攻撃の標的になりやすい。 |
| 怪しいサイトやメールを開かない | 不審なリンクや添付ファイルはマルウェア感染の入り口となるので注意。心当たりのない送信元からのメールは開かず、公式サイトで情報を確認。 |
| フリーWi-Fiの利用を避ける | 暗号化されていない公衆Wi-Fiは通信内容が盗み見られる危険が高い。利用する場合、重要な操作は控え、IDやパスワード入力を求められる際は利用を避ける。 |
| 個人情報をWeb上に公開しない | 公開された断片的な情報から、住所や金融情報が特定されるケースも。SNSの公開範囲設定を見直し、不要な個人情報は公開しない。 |
| ウイルス対策ソフトを導入する | マルウェアの侵入を未然に防ぎ、感染時の駆除にも役立つ。ただし、万能ではないため、他の対策と併用することが重要。 |
これらを習慣化すれば、ハッキングのリスクを大幅に減らせます。
大切な資産や個人情報を守るために、自衛する術も身につけましょう。
ハッキングを防ぐには日頃の対策が重要

ハッキングは、被害に遭ってから対処するよりも、日頃の予防策で未然に防ぐことが重要です。
OSやアプリのアップデート、怪しいメールやサイトを開かない、信頼できるセキュリティソフトを導入するなど、基本的な対策を継続するだけでもリスクは大幅に減らせます。
また、万が一被害が発生した場合に備えて、カード利用明細の定期確認や二要素認証の設定など、早期発見につながる行動も習慣づけておくと安心です。
被害を完全にゼロにすることは難しいものの、日々の小さな心がけが大きな防御力となります。
「自分は大丈夫」と思わず、今すぐ取り入れられる対策から始めましょう。
