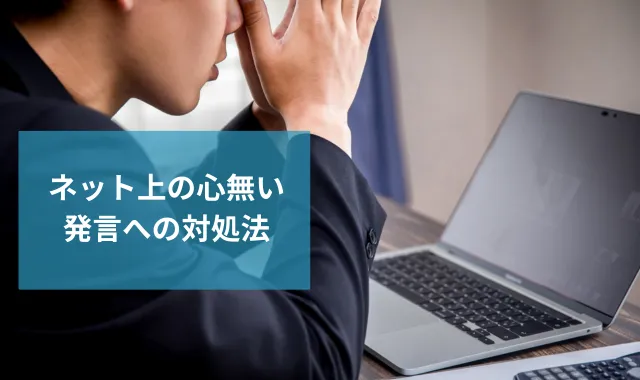
どこからが誹謗中傷に当たる?ネット上の心無い発言への対処法
しかし、誹謗中傷という言葉は知っていても、「具体的にどのような言動が誹謗中傷に当たるのか、よく分からない」と感じている方もいるのではないでしょうか。
また、「ネット上で第三者から心無い発言をされたが、これが誹謗中傷を受けたと言っていいのか自信がない」と悩んでいる方も多くいます。
この記事では、さまざまな誹謗中傷のケースを具体的に紹介しています。
誹謗中傷を受けた際の適切な対処法についても記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも誹謗中傷とは?

最初に、誹謗中傷という言葉の意味について解説します。
誹謗中傷の定義や、誹謗中傷と批判の違いについては以下のとおりです。
誹謗中傷の定義
そもそも「誹謗中傷」という言葉は、法律用語ではありません。
「誹謗」と「中傷」を合わせた造語といわれています。
「誹謗」の意味は「他人を悪く言うこと」「非難すること」です。
「中傷」の意味は「根拠のないことを言いふらし、他人の名誉を傷つけること」です。
つまり、誹謗中傷は「根拠なく他人のことを悪く言い、他人の名誉を傷つけること」という意味になります。
例えば、「あいつはゴミ」「◯◯は無能」などの言葉は、誹謗中傷に該当します。
加えて、誹謗中傷の大きな特徴として、人格攻撃をしている点が挙げられます。
人格攻撃とは、相手の人格、性格、外見、存在そのものを否定し、攻撃する言動のことをいいます。
このような人格攻撃をする言動はすべて、誹謗中傷に該当します。
誹謗中傷と批判の違い
誹謗中傷と似た言葉として「批判」があります。
しかし、誹謗中傷と批判は似て非なるものです。
「批判」の意味は、「ものごとの真偽や可否を検討し、評価・判定すること」です。
すなわち、「他人の言動に対し、その誤りを指摘し、正すよう求めること」と解釈することができます。
「批判」の一例としては、「コロナの感染者が増加しているにも関わらず、日本がオリンピックを開催するのはおかしい」という意見がこれに当たります。
誹謗中傷と批判の違いとしては、誹謗中傷は、相手の人格そのものを攻撃する発言で、相手に対する明確な悪意が含まれる一方、批判は、相手の行動や発言内容への意見・論評であり、人格攻撃ではありません。
誹謗中傷に対する刑事上の責任
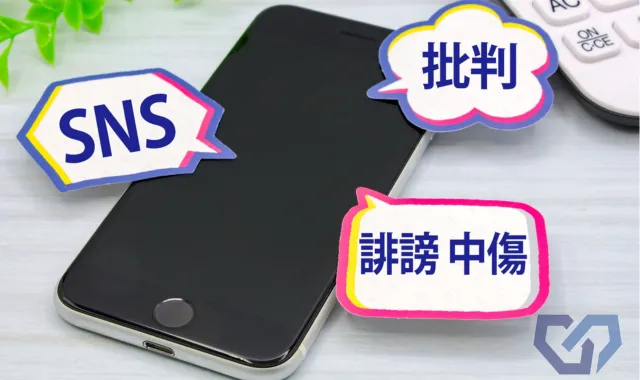
誹謗中傷について、法律的に明確な線引きがあるわけではありませんが、内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪、信用毀損罪などの罪に問われる可能性があります。
名誉毀損罪
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が、「その事実の有無にかかわらず」該当する罪です。(刑法230条)
「公然と」が要件とされているため、第三者が見ることができない個人間のメッセージのやり取りの中での誹謗中傷は、原則としてこの罪には該当しません。
また、「事実を摘示」したことが要件となっているため、抽象的な批判や悪口は名誉毀損罪の対象外です。
ただし、「その事実の有無にかかわらず」とされているため、たとえ事実無根の内容であっても、名誉毀損罪は成立し得ます。
さらに、「人の名誉を毀損」したことが必要であるため、被害者が主観的に傷付いていたとしても、社会的評価が低下したと判断されなければ、名誉毀損罪は成立しません。
名誉毀損罪を犯した者は、3年以下の懲役、50万円以下の罰金の刑罰に処されます。
名誉毀損罪の例として、「〇〇は不倫している」という情報を拡散するなどの行為が挙げられます。
この場合、不倫の事実が真実でも虚偽でも名誉毀損罪に問われる恐れがあります。
侮辱罪
侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱」した場合に該当する罪です(同231条)
名誉毀損罪と似ていますが、「事実の摘示」が不要とされており、抽象的な誹謗中傷であっても該当する可能性があります。
侮辱罪を犯した者は、1年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留・科料のいずれかの刑罰に処されます。
なお、侮辱罪は、令和4年(2022年)7月6日まで「拘留または科料」のみの刑罰でした。
しかし、SNS上で誹謗中傷を受けたプロレスラーの女性が自ら命を絶った事件を受け、刑罰が軽すぎると世論からの批判が生じたことから、厳罰化されています。
侮辱罪の例として、「うざい」「馬鹿」「きもい」などの抽象的な悪口や、「ハゲ」「ブス」といった身体を揶揄する悪口などが該当します。
脅迫罪
脅迫罪とは、相手の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」した場合に該当する罪です。(同222条)
脅迫罪を犯した者は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。
脅迫罪は、名誉毀損罪や侮辱罪とは異なり、「公然と」行うことは要件とされていません。
そのため、個別のメッセージなど第三者の目に触れない場での発言であっても、脅迫罪の対象となる可能性があります。
信用毀損罪・偽計業務妨害罪
信用毀損罪や偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」した場合に該当する罪です。(同233条)
たとえば、嘘の口コミを書いてお店や会社の評判を下げたり、業務を妨害したりした場合には、この罪に該当します。
信用毀損罪や偽計業務妨害罪を犯した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。
偽計業務妨害罪の例としては、「自分はコロナに感染している」と嘘をつき、病院や施設に不必要な消毒の負担を負わせる、などが該当します。
信用毀損罪の例としては、「あの会社は倒産寸前だ」といったデマの情報を拡散する、などが該当します。
誹謗中傷に対する民事上の責任

誹謗中傷に対するもう一つの法的措置として、民事上の損害賠償請求があります。
損害賠償請求とは、相手の行為によって被った物的・精神的な損害を、金銭で賠償させる請求をいいます。
誹謗中傷に対して損害賠償請求をするためには、まずは加害者を特定しなければいけません。
誹謗中傷の発信者が匿名のアカウントのような場合は、発信者情報開示請求などを行って相手を特定しなければなりません。
なお、インターネット上の書き込みに関しては、平成14年5月27日に施行されたプロバイダ責任制限法によって、発信者情報の開示請求が認められています。
誹謗中傷に該当するケースの紹介
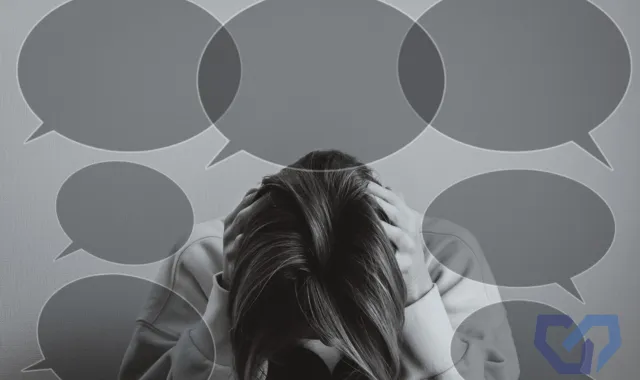
ネットが普及した現在、誹謗中傷によるトラブルは増加傾向にあります。
ここでは、実際に誹謗中傷を受けて裁判に至ったケースをご紹介します。
ネット上で脅迫をしたケース
漫画家であるAさんは、自分が描いたイラストが無断転載されていることを知り、投稿者に削除するよう求めました。
しかし、投稿者はそれを拒否し、逆にAさんに対して「Aから脅迫された」と誹謗中傷を行いました。
このケースは、加害者に対して名誉毀損罪の判決が下され、慰謝料30万円の支払いと、著作権侵害による損害20万円の支払い命令が下されました。
イラストや写真などの画像は、フリー素材と明記されていない限り著作権が発生します。
このケースでは結果として、誹謗中傷による名誉毀損として慰謝料だけではなく、投稿者へ著作権侵害による損害料も発生しました。
SNS上に悪口を書き込んだケース
20代女性の麻雀士Bさんは、SNS上で匿名のアカウントから、「Bは整形雀士」との書き込みや、容貌や異性関係について屈辱的なコメントを受けました。
結果、加害者に対して名誉毀損罪の判決が下され、Bさんへ100万円の損害賠償の支払いが命じられました。
このケースのように、容姿や異性関係に関する悪意ある書き込みで、社会的評価を低下させた場合には、名誉毀損罪が成立する場合があります。
まとめサイトの管理人が責任を問われたケース
外国人のCさんは、自国の文化や国民に対して差別的な内容の文章を作成・編集し「まとめサイト」で不特定多数へ発信したとして、まとめサイト管理人に対し2,200万円の支払いを要求しました。
結果として、まとめサイトの管理人に対して、200万円の損害賠償の支払いが確定しました。
このケースのように、外部で記載されている情報を「まとめサイト」として一つの記事にした場合、たとえ自筆していなくとも誹謗中傷に該当します。
誹謗中傷を受けたら

ネット上などで誹謗中傷を受けていると感じたら、放置せずに適切な対処方法を取る必要があります。
誹謗中傷はエスカレートする可能性があるため、早急な対応が肝心です。
確実に証拠を残す
ネット上で誹謗中傷の被害に遭ったら、まずは証拠を残しましょう。
確実な証拠がなければ、裁判所への発信者情報開示請求などが難しくなってしまうからです。
証拠を残す方法としては、
- 誹謗中傷の内容
- 書き込みがあった日時
- 投稿されたサイトのURL
- 加害者のユーザー名やアカウント
以上の内容がわかるスクリーンショットを撮影する方法などが考えられます。
加害者を特定する
ネット上の誹謗中傷を訴えるためには、加害者を特定していることが重要になります。
加害者の個人情報の開示請求は、現時点では裁判所に訴訟を提起する必要がありますが、通常、裁判手続きによってインターネットのプロバイダから加害者の個人情報の開示を受けられるまでには、6ヶ月〜1年程度の期間がかかります。
迅速に加害者を特定したい場合は、探偵などの専門家に依頼することを検討しましょう。
サイト管理者に削除依頼をする
該当する投稿や書き込みの証拠をスクリーンショットや印刷などで残した後、サイトの管理人等に誹謗中傷コメントの削除の依頼をしましょう。
ただし、管理人によっては、表現の自由を理由に削除に応じてくれないケースもあります。
サイトの管理人が削除に応じてくれない場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的な手段を取ることも検討しましょう。
法的措置を検討する
法的手続きを取る場合は、弁護士に依頼すると、法的な観点からのアドバイスをもらえたり、手続きを代行してくれます。
裁判手続きを行う場合、誹謗中傷を受けた証拠を集めておくことが重要になります。その際、探偵に依頼することで、スムーズに証拠収集ができることが期待でき、お勧めです。
誹謗中傷被害の調査は探偵への依頼がお勧め

先述のとおり、誹謗中傷の投稿者が匿名のアカウントのような場合、自力で加害者を特定することは非常に困難です。
また、加害者の個人情報の開示請求を裁判所に申立てた場合、実際に情報が開示されるまでに、6ヶ月〜1年程度の期間がかかってしまいます。
探偵に加害者調査を依頼した場合、プロの調査能力を駆使するため、迅速に加害者特定ができる可能性が高まります。
探偵が誹謗中傷被害の調査でできることは、以下のとおりです。
- 誹謗中傷の具体的な証拠を保全する
- 誹謗中傷コメント・ウェブサイト・投稿の削除要請の代行
- 加害者の特定
- 加害者の素性、被害者との接点の調査
- 被害者と犯人の繋がり・接点の調査 など
探偵は、インターネットに関する高度な専門知識と、情報収集・分析のための様々なツールを保有しています。
SNSやブログなどで生じたトラブルはもちろん、一般にはアクセスしにくいダークウェブなど、特殊なプラットフォームでの調査にも対応しています。
探偵であれば、個人ではアクセスが困難な場所にあるデータ収集も可能なため、問題解決までの時間を大幅に短縮できる可能性があります。
誹謗中傷でお悩みの方は当探偵事務所までご相談ください

悪質な誹謗中傷は、被害者の心身に大きなダメージを与えます。
ネット上で心無い発言を受けて悩んでいる方、法的手続きを取りたいけれど、証拠収集や加害者特定の段階で足踏みしている方は、まずはご相談だけでも、当社までご連絡ください。
誹謗中傷のない平穏で安全な日々を取り戻すため、当探偵事務所が全力でサポートいたします。
ご相談は、お問合せフォーム・電話・メール・LINEにて24時間お受けしています。
