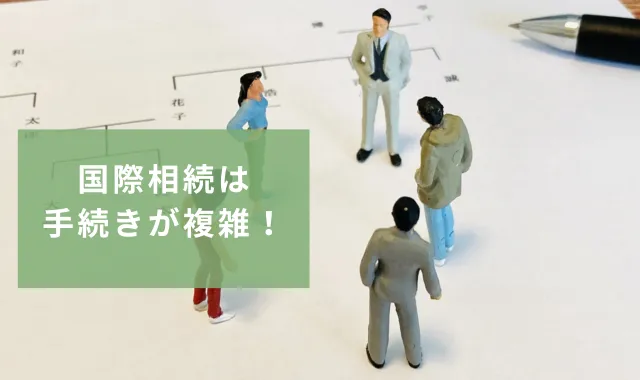
国際相続は手続きが複雑!具体的な事例や注意点を徹底解説
くわえてこれが、国際相続で海外に国の法律や手続きが関連するとなると、複雑なステップを踏んで対応しなければなりません。
国際相続を乗り越えられるか、不安な方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、国際相続の概要やルール、手続きなどが複雑になりやすい理由について解説します。
また、相談すべき専門業者も紹介します。
ぜひ最後までチェックしてください。
国際相続基本的な考え方

国際相続とは、被相続人(亡くなった方)や相続人、または財産が複数の国にまたがる場合に国際相続となり、一般的な国内の相続とは比べ物にならないほど複雑になるのが特徴です。
特に、被相続人が海外に住んでいたり、相続人の中に海外に住む方がいたりするケースや、海外に不動産や預貯金といった財産があったりするケースでは、適用される法律や手続きが複雑になります。
複数の国の法律や税制が関係してくるため、専門知識なしで対応するのは困難です。
例えば、日本の法律では問題なく進められる手続きが、相手国の法律ではまったく通用しないということも珍しくありません。
トラブルを避けるためにも、事前に正確な情報を把握しておくことが重要です。
国際相続は、適用される法律や相続税の計算方法が国ごとに異なるため、専門家の力が不可欠だといえるでしょう。
国際相続の基本的なルール
国際相続の基本として、日本国内に存在する財産は、被相続人や相続人の国籍・居住地に関わらず、原則として日本の相続税が課せられます。
これは、国内に存在する財産に対して日本の法律が優先的に適用されるといった、基本的な考え方に基づいています。
土地や建物といった不動産はもちろん、現金や預貯金、株式や債券などの有価証券が課税対象の財産です。
例えば、被相続人が長年海外に住んでいたとしても、日本国内に実家やマンションを所有している場合、その不動産には日本の法律が適用されるため、相続税の計算対象となるのです。
また、日本の金融機関に預けられている預貯金も同様に、日本の相続税の対象となります。
日本の相続法は、日本の土地にある財産を守るために「財産所在地主義」という考え方を採用しています。
そのため、国際相続の場合でも、まずは日本国内にある財産について正確に把握し、日本の税務署に申告することが最初のステップとなります。
海外資産へは海外の法律が適用されるケースも
一方、海外にある財産には、その所在地国の法律や税制が適用されるケースがあります。
特に不動産は、その所在地国の法律が優先されるのが一般的です。
例えば、ハワイに別荘を所有している方が亡くなった場合、その別荘の相続手続きはハワイの法律に則って進めなければなりません。
また、海外の銀行に預金がある場合も、その国の法律や銀行のルールに従って手続きを進める必要があります。
海外での相続手続きには、日本とは異なる独自の書類や手順が求められることが多いため、手間と時間がかかるものと考えておきましょう。
状況によっては、現地の弁護士や専門家を雇う必要がある場合もあり、手続きが完了するまでに長い時間がかかることも覚悟しなければなりません。
このように、海外資産の相続には、その国特有の複雑な手続きや税制を理解し、適切な対応が必要です。
特に、海外に財産がある場合は、日本国内の手続きに加えて、同時に海外の手続きも進めなければならず、対応はとても複雑になります。
日本の相続法における適用法の原則
日本では、死亡者が日本の国籍を持っていれば、相続は日本の法律に従って手続きを行います。
また、死亡者が外国籍の場合、その本国法が用いられます。
ただし、財産に関しては、海外の国籍を持つ人が死亡しても、日本国内に存在する財産に関しては日本の法律が用いられるケースもあります。
専門家などに相談して、財産に影響する法律を把握する必要があるでしょう。
また、注意すべき点として、相続人の国籍や住んでいる場所が影響するケースがあります。
一例は以下の通りです。
| 死亡者の国籍 | 相続人の国籍 | 用いられる法律 |
| 日本 | アメリカ | アメリカ |
相続人の国籍や状況などによって異なるものの、相続人に外国籍者が存在するなら、その人の本国法が用いられる可能性があり、手続きなどが複雑になります。
こちらも専門知識を持つ業者に対応を依頼するなどの対策が必要です。
国際相続の発生時は、用いられる法律がどの国のものかが重要であるため、必ずチェックして正確に把握しておきましょう。
国際相続が複雑になりやすい3つの理由

国際相続は、一般的な相続と比較して、複雑になりやすいという特徴があります。その理由は次の通りです。
- 国によって適用される法律が異なるか
- 国によって相続財産に対する主義が異なるから
- 反致が適用されるか確認する必要があるから
それぞれ詳しく解説します。
国によって適用される法律が異なるから
国際相続が複雑になる最大の理由の一つは、国ごとに相続に関する法律が大きく異なるためです。
財産の分配方法、法定相続人の範囲、遺留分の有無など、日本の法律と海外の法律には大きな違いがあります。
例えば、日本では配偶者や子に法定相続分や遺留分が保障されていますが、国によっては遺言書がすべてに優先され、家族の権利が全く保障されない場合があります。
また、財産を誰にどのように分配するかというルール自体が、文化や宗教観によって日本と異なることも珍しくありません。
そのため、準拠法(どの国の法律を適用するか)の確認を怠ってしまうと、予期せぬトラブルや、本来受け取れるはずの財産が不当に分配されてしまう事態に繋がりかねません。
国際相続の手続きを始める前に、必ず被相続人の本国や財産の所在地国の法律を十分に調査し、準拠法を特定することが重要です。
準拠法を間違えると、すべての手続きをやり直すことになり、時間と費用が無駄になってしまう可能性があるため、注意しましょう。
国によって相続財産に対する主義が異なるから
国際相続の複雑さを増すのは、相続の対象となる財産への考え方が、国ごとに異なるためです。
各国は以下のいずれかの主義を採用しています。
- 相続財産全体を一括で扱う統一主義
- 動産と不動産で用いられる法律が異なる分割主義
統一主義とは、財産の所在地に関係なく、相続財産のすべてを一体として扱い、用いる法律を決めるという考え方です。
一方、分割主義とは、不動産には所在地の法律、動産には本国または住所地の法律を用いるというように、財産の種類によって用いる法律が違うという考えです。
日本は統一主義になるため、日本の国籍を持つ人が死亡した場合、海外にある財産でも日本の法律が用いられます。
また、海外の国籍を持つ人が無くなった場合は、その人にとっての本国の法律が用いられます。
日本の他には韓国やドイツなどが、統一主義となっています。
一方、海外の国では分割主義となるケースがあります。
アメリカやフランス、イギリス、中国などでは、相続分割主義となっています。
このような違いを分かっておかないと、いくつかの国に財産がある場合、どの法律を適用するのかわからず、手続きが迷走する原因となります。
反致が適用されるか確認する必要があるから
「反致」という考え方も、国際相続が複雑になる要因の一つです。
反致とは、国際私法(国をまたぐ法律の問題を解決するためのルール)における概念です。
具体的には、ある国の法律が、他国の法律を用いると指定するケースで、その指定された国の法律がさらに元の国の法律を用いると指定しているケースを指します。
簡単に言えば、A国籍を持つ人が住むB国で「あなたの国(A国)の法律を用いる」と法律で決めているにもかかわらず、A国で「元の国(B国)の法律を使いなさい」と法律で決められているのが反致です。
つまり、用いる法律が一周して元に戻る状況を指します。
よりわかりやすくするために、日本に住む中国人が亡くなり、相続となる例を紹介します。
- 日本では、外国籍の人の相続に対し、その人の国の法律を使う(中国の法律で相続の手続きを進める)
- ただし、中国では不動産の相続は不動産の所在地の法律を用いると決めている
- 日本の不動産には、日本の法律を用いることになる
この場合、日本方式の相続の手続きとなるため、国際相続と比べて手続きが簡単になります。
ただし、反致の条件は国によって異なるほか、専門的な判断が必要なため、一般の方が自力で判断するのは難しいといわざるを得ません。
国際相続で考えられる具体的なケース5選

国際相続は、被相続人や相続人の状況から、さまざまなケースが考えられます。
ここでは、国際相続で考えられる以下のような具体的なケースについて紹介します。
- 日本国内で海外資産を含めた財産を相続するケース
- 海外に住む親が死亡して日本に住む子が相続するケース
- 日本に住む親が死亡して海外に住む子が相続するケース
- 日本国籍を所有する家族が海外へ移住してから相続が発生したケース
- 海外に住む相続人がその国の国籍を取得しているケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
日本国内で海外資産を含めた財産を相続するケース
このケースでは、まず日本国内にある財産について、日本の相続税法に基づいて相続税の申告と納税を行います。
また、並行して海外にある財産についても、その財産の所在地国の法律や税制に沿った手続きを進めていかなければなりません。
例えば、海外に所有する不動産の名義変更を行うには、その国の法律に基づいた相続手続きが必要になります。
なお、アメリカなどでは、遺言書の有効性を確認し、遺産を管理・分配する裁判所の手続きを完了させないと、不動産の名義変更や銀行預金の引き出しができない場合があります。
この手続きのことを「プロベート」といいます。
日本の税務当局への申告と海外の税務当局への申告を両方行う必要があるため、両国の手続きを円滑に進めるには、国際的な専門知識を持つプロのサポートが不可欠です。
また、二重課税を避けるための租税条約や外国税額控除の適用も考慮しなければならないため、複雑な手続きとなることを理解しておきましょう。
海外に住む親が死亡して日本に住む子が相続するケース
この場合、被相続人(亡くなった親)が海外に住んでいたため、まずは被相続人の本国法に従って相続手続きを進める必要があります。
被相続人の国籍国の法律や居住していた国の法律が適用される可能性があるからです。
そのため、日本の法律だけでは対応できないことが多いといえます。
例えば、被相続人がアメリカ国籍であれば、アメリカの相続法が適用されるのが一般的です。
アメリカの相続法が適用される場合、遺言書の有効性や相続人の範囲、財産の分配方法など、すべてアメリカの法律に従って進めなければなりません。
また、海外での相続手続きに必要な書類として、現地の相続証明書や公証書などを準備する必要があり、これらは日本の公的書類とは異なる形式や手続きを要します。
書類の翻訳や公証手続きに時間がかかることも多いため、手続きがスムーズに進まない可能性も考慮しなければなりません。
このようなケースでは、現地の弁護士や専門家との連携が必須となり、日本の専門家と協力して対応にあたる必要があるでしょう。
日本に住む親が死亡して海外に住む子が相続するケース
このケースでは、被相続人は日本に住んでいたため、日本の法律が相続の準拠法となるのが一般的です。
しかし、海外に住む相続人(子)は、日本の相続手続きに加え、住む国の相続関連の手続きも必要になる場合があります。
住む国によっては、日本の相続財産に対して別途課税される可能性があるため、二重課税のリスクに注意しなければなりません。
例えば、アメリカに住む相続人は、日本の相続税の支払い後に、アメリカの連邦遺産税や州の遺産税の支払いが求められることがあります。
このような二重課税を避けるためには、外国税額控除の手続きを適切に行う必要があります。
海外に住む相続人が日本での相続を円滑に進めるためには、相続の知識に加え、住む国の税制の知識を持つ専門家の協力が欠かせません。
日本国籍を所有する家族が海外へ移住してから相続が発生したケース
日本国籍を持つ家族が海外へ移住した後に相続が発生した場合、日本の相続税法上の「居住者」か「非居住者」かの判断が重要になります。
この判断によって、課税される財産の範囲や税金の計算方法が大きく変わるためです。
例えば、日本の相続税法における非居住者と判断されると、日本国内にある財産にのみ相続税が課税されますが、居住者と判断された場合は、国内外のすべての財産が課税対象となります。
また、移住先の国の法律が優先されるか、日本の法律が適用されるか、という準拠法の複雑な判断も同時に求められます。
滞在期間や居住の意思、生活の本拠地など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断されるため、どちらに該当するのか専門家による慎重な判断が必要です。
このように、移住後の相続は、日本の相続税法と移住先の国の法律、両方に精通していなければ適切な対応が難しいといえます。
海外に住む相続人がその国の国籍を取得しているケース
海外に住む相続人が、居住国の国籍を取得している場合、その国の法律が相続に強く影響を与えることになります。
被相続人の本国法と相続人の国籍法が異なるため、どの国の法律が適用されるか、準拠法が複雑になるからです。
例えば、被相続人が日本国籍で、相続人がアメリカ国籍を取得している場合、日本の法律とアメリカの法律のどちらを適用すべきかという問題が生じます。
遺言書があれば、その内容が有効であるかどうかも、両国の法律で判断される必要があります。
特にアメリカでは、州ごとに法律が異なるため、さらに複雑さが増すでしょう。
このようなケースでは、日本の法律に精通した専門家だけでなく、居住国であるアメリカの弁護士や専門家と綿密に連携しなければなりません。
両国の専門家が協力し、それぞれの法律や手続きを正確に理解することで、スムーズな相続手続きを進められるでしょう。
個人の国籍が変わるだけで、相続手続きの難易度は格段に上がることを、理解しておきましょう。
国際相続が発生する場合に備えておきたい3つの準備

国際相続が発生する可能性がある場合は、事前にある程度の準備をしておくことが重要です。
具体的には、以下のような準備を進めておきましょう。
- 財産目録の作成を進める
- プロベートの有無を確認する
- 信頼できる相談先を見つけておく
それぞれ詳しく解説します。
財産目録の作成を進める
国際相続では、国内の財産だけでなく、海外にある財産も含めて正確な財産目録を作成することが大切です。
財産目録とは、個人や法人が所有する財産を一覧でまとめた書類資料を指します。
相続手続きの全体像を把握するための羅針盤となる、重要な書類です。
財産の種類(不動産、預貯金、有価証券など)、所在地国、おおよその価値などを詳細にリストアップしておくことで、相続に関連する全体像がわかりやすくなります。
特に、海外の財産は、存在が把握しづらいことが多いため、預金口座の通帳や不動産の権利証など、証拠となる書類をすべて整理し、リストに加えることが大切です。
もし、被相続人の財産が不明な場合は、国際的な調査ネットワークを持つ専門家への依頼も検討すべきでしょう。
財産目録が準備されていれば、各国の法律や税制に沿った対応を計画することができ、手続きの漏れや不備の防止が可能です。
この準備を怠った場合、後から新たな財産が見つかると、手続きをやり直すことになりかねないため、注意しましょう。
プロベートの有無を確認する
プロベートとは、主に英米法圏で採用されている、遺産の法的手続きのことです。
死亡した人の遺言が有効か裁判所が確認して、遺産の管理や分配を監督する制度で、
遺言が存在する場合、正しい手続きで作成されているかを裁判所が確認します。
一方、遺言がない場合は、州法や国の法律などに基づき、裁判所が相続人の確定と分配を決める仕組みです。
実際の手続きでは、裁判所への申し立てを行い、裁判所が遺言の有効性の確認や遺産の調査、評価を行います。
その後、個人の債務や税金の未払い分を精算し、遺言や法律の規定に従って残りの財産を相続人へと分配します。
特に、アメリカでは、被相続人が不動産や預金を単独名義で所有していた場合、プロベートが必要になるケースがほとんどです。
プロベートは裁判所が関与するため、公平性が担保される一方で、時間と費用がかかるデメリットがあります。
手続き開始から遺産の分配完了まで、半年から数年程度かかるケースがあることに加え、弁護士費用・裁判所費用などで、遺産の数%から10%程度が失われることもあります。
また、手続きが複雑になりやすいため、被相続人の国の法律でプロベートが必要か、事前に確認しておくことが重要です。
必要な場合は、被相続人の生前にプロベート回避のための対策(例えば、信託の設定など)を講じておくことも有効な手段となります。
専門家と相談し、プロベートの有無や手続きの流れを把握しておくことで、将来の負担を大きく軽減できるでしょう。
信頼できる相談先を見つけておく
国際相続は、手続きが複雑で専門知識が不可欠なため、信頼できる専門家へ相談することが重要です。
国際相続に精通した弁護士、税理士、行政書士などを早めに見つけておくことをおすすめします。
また、海外に住む相続人探しや身辺調査は、国際相続に強い探偵事務所に調査を依頼するのも一つの手段です。
国際相続の専門家は、単に日本の法律だけでなく、海外の法律や税制にも詳しいため、さまざまな問題に適切に対応してくれます。
さらに、現地の弁護士や専門家とネットワークを持つ業者を選ぶと、海外での手続きもスムーズに進められるでしょう。
相談先を選ぶ際には、その専門家が国際相続の実績を豊富に持っているか、丁寧な説明をしてくれるかなどを基準にしましょう。
国際相続での主な注意点

国際相続は、国境を越えた相続手続きが必要になることから、国内相続とは違った点に注意しなければなりません。
それぞれ詳しく解説します。
相続に対する準拠法を確認しなければならない
国際相続において、重要かつ見落とされがちなのが「準拠法」の確認です。
準拠法とは、相続に関する法律をどの国のものにするかというルールを指します。
被相続人の本国法、被相続人の居住地法、財産の所在地法など、準拠法となる候補は複数あり、状況によって適用される法律が異なるため、注意が必要です。
例えば、被相続人が日本国籍で海外に住んでいて、日本に財産がある場合、準拠法は日本の法律となるのが原則ですが、被相続人の居住地法の適用を求める場合もあります。
準拠法の特定を誤ってしまうと、相続人の範囲や財産の分配方法が日本の法律と大きく異なり、手続きのやり直しや予期せぬトラブルに発展する可能性があります。
事前に専門家へ相談し、被相続人の国籍、居住地、財産の所在地などの情報を正確に伝え、どの国の法律が適用されるかを確定させてから手続きを進めることが大切です。
遺言の有効性が国によって異なる
国際相続では、遺言書が有効と認められるための要件が国によって大きく異なります。
日本では自筆証書遺言や公正証書遺言といった特定の方式が定められていますが、海外では異なる形式や手続きが求められる場合があります。
例えば、日本では公的に認められる公正証書遺言でも、海外では形式の不備を理由に無効と判断されるケースがあるのが実状です。
そのため、国際相続に関連する国や、地域に適した遺言書を作成しなければなりません。
複数国に財産がある場合は、各国の方式に準拠した遺言書を作成するか、専門家と相談して対応を検討したほうがいいでしょう。
遺言書が有効と認められない場合、財産の分配が法定相続分に従って行われることになり、被相続人の意図が反映されなくなってしまいます。
また、手続きが複雑化し、時間と費用が余計にかかることにもつながります。
国際相続では、遺言書を作成する段階から、複数の国の法律に精通した専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
二重課税を回避しなければならない
国際相続では、複数の国で相続税が課税され、結果的に二重に税金を支払うリスクがあります。
そのため、二重課税の回避策を講じることが重要です。
例えば、日本の相続税法では、被相続人や相続人が日本に住所を持っていれば、国内外のすべての財産に日本の相続税が課税されます。
一方で、財産がある海外の国でも、その国の法律に基づいた相続税が課税される場合があります。
このような二重課税を回避するため、多くの国が互いに締結しているのが「租税条約」です。
租税条約とは、二重課税を防止するためのルールを定めたものです。
租税条約の活用によって、海外で支払った相続税を日本の相続税から控除できる「外国税額控除」の適用を受けられます。
ただし、手続きが複雑なほか、すべての国との間で租税条約が締結されているわけではない点には注意が必要です。
専門家と協力し、外国税額控除の適用を受けるための要件や手続きを正確に把握して、二重課税を回避し、財産を守りましょう。
国際相続では海外調査が不可欠

国際相続では財産や法律の取扱いが、国内での相続とは大きく異なります。
特に、海外にいったことがない場合、現地の財産や相続人の詳細などを調べるのは、かなり難しくなるでしょう。
そこで重要になるのが、探偵による海外調査です。
ここでは、国際相続で欠かせない海外調査について詳しく解説します。
国際相続で必要な海外調査とは
国際相続における海外調査とは、海外にある財産の詳細や、その所在国の法律、税制、手続きなどを詳しく調べることを指します。
海外調査は、現地の銀行口座の有無や、不動産の名義変更に必要な書類、手続きの具体的な流れを特定するために行われます。
また、遺産隠しや被相続人自身も把握していなかった不明な財産がないかを確認する目的で行われることもあります。
海外での情報収集は、言葉の壁や現地の法律・商習慣の違いから、個人で行うのは非常に困難です。
現地での情報収集には、専門的な知識とネットワークが不可欠であり、適切な調査を行わないと、財産の全容が掴めず、手続きが滞る原因になります。
そのため、国際相続を円滑に進めるうえで、海外調査は避けて通れない重要なステップといえます。
海外調査は専門知識を持つ業者に依頼するのがおすすめ
個人で海外調査を行うのは、語学力や現地の法律知識の面から、難しいといわざるを得ません。
例えば、海外の不動産登記簿を調べるだけでも、その国の公的機関へのアクセス方法や必要書類が分からず、手続きが進められないことが多々あります。
そのため、国際相続に特化した探偵事務所や調査会社、弁護士事務所など、海外にネットワークを持つ専門業者に依頼するのが効率的で確実な方法です。
専門業者は、現地の法律家や調査員と連携し、迅速かつ正確に財産情報を収集するノウハウを持っています。
専門業者に依頼することで、遺産隠しや不明な財産を特定できる可能性が高まり、後の相続手続きを円滑に進められます。
信頼できる専門家を見つけて海外調査を依頼すれば、国際相続の複雑なプロセスを安心して進められるでしょう。
国際相続は専門家へ相談しながら進めよう

国際相続は、国境を越えるため、日本の相続とは比較にならないほど複雑で、多くの専門知識が求められます。
適用される法律、税制、手続き、そして財産の所在国ごとの特有のルールなど、考慮すべき点が多岐にわたるため、個人の力だけで円滑に進めるのはほぼ不可能です。
特に、海外にある財産を把握したり、相続人の所在を特定したりする「海外調査」は、手続きの成否を分ける重要なポイントとなります。
もし、国際相続に関して、どこに財産があるのかわからない、相続人の中に連絡が取れない人がいる、といったお悩みがある場合は、国際相続の専門家に相談することをおすすめします。
なお、国際相続における海外調査が必要なら、西日本ファミリー探偵事務所にご相談ください。
同事務所は、国際相続のプロセスにおいて不可欠な、相続人の探し出しや海外調査を得意としています。
世界各地の調査ネットワークを駆使し、行方不明の相続人や被相続人の海外財産の効率的な特定が可能です。
国際相続は、日本の法律だけでなく、海外の法律や税制にも精通していなければ適切な対応が難しくなりますが、当探偵事務所は海外調査に強いため、さまざまな悩み・課題に対応できます。
一人で悩まずに、まずはプロに相談してみることで、国際相続の道筋が見えてくるでしょう。
